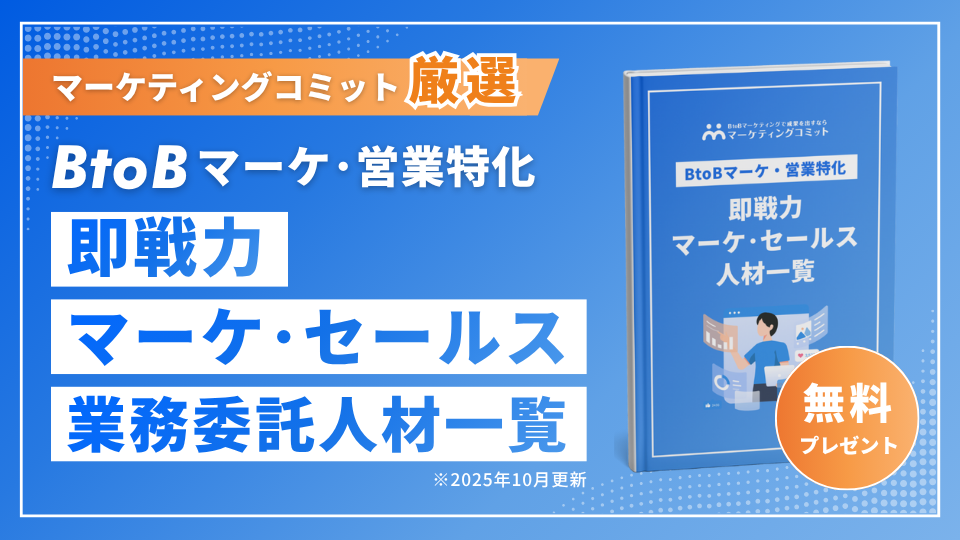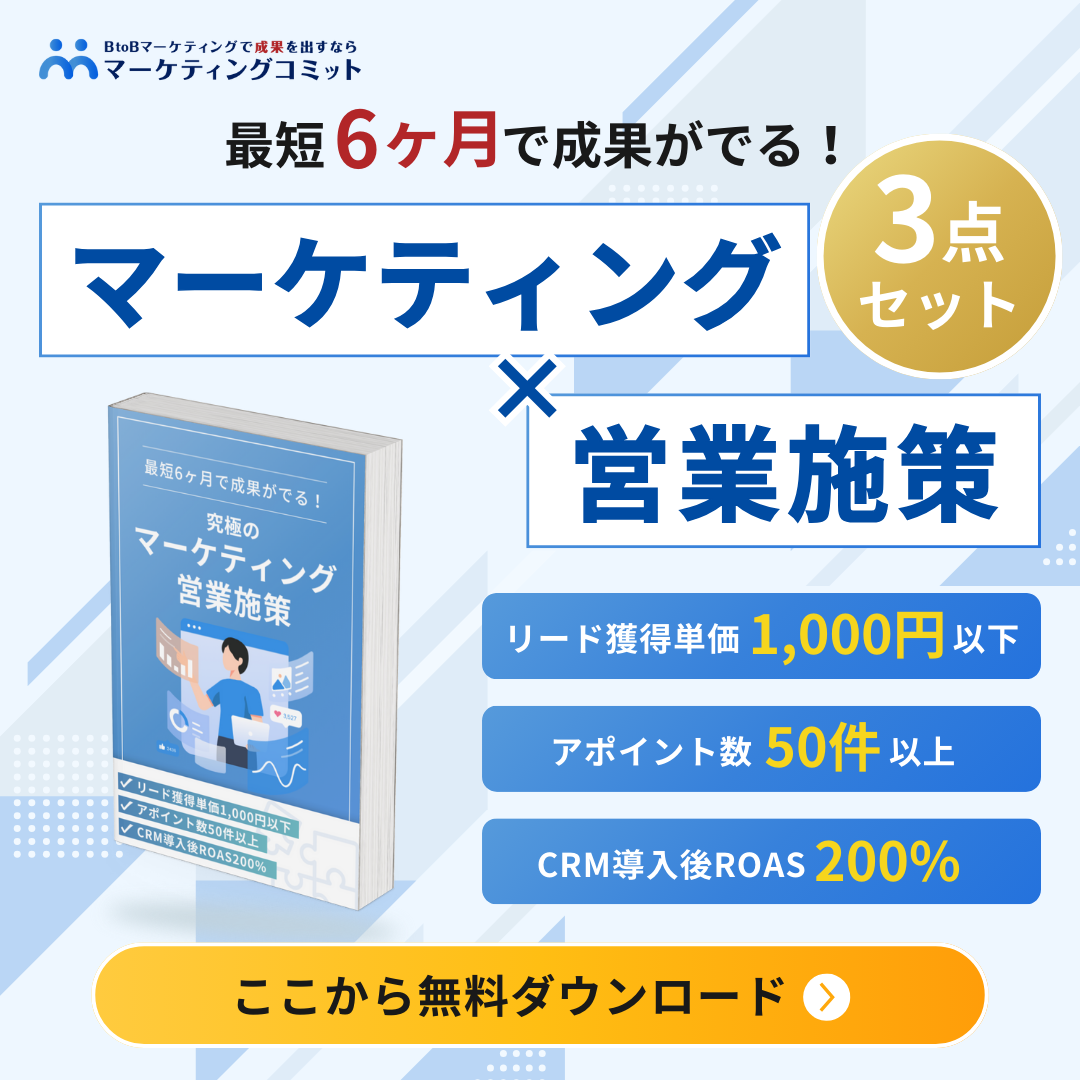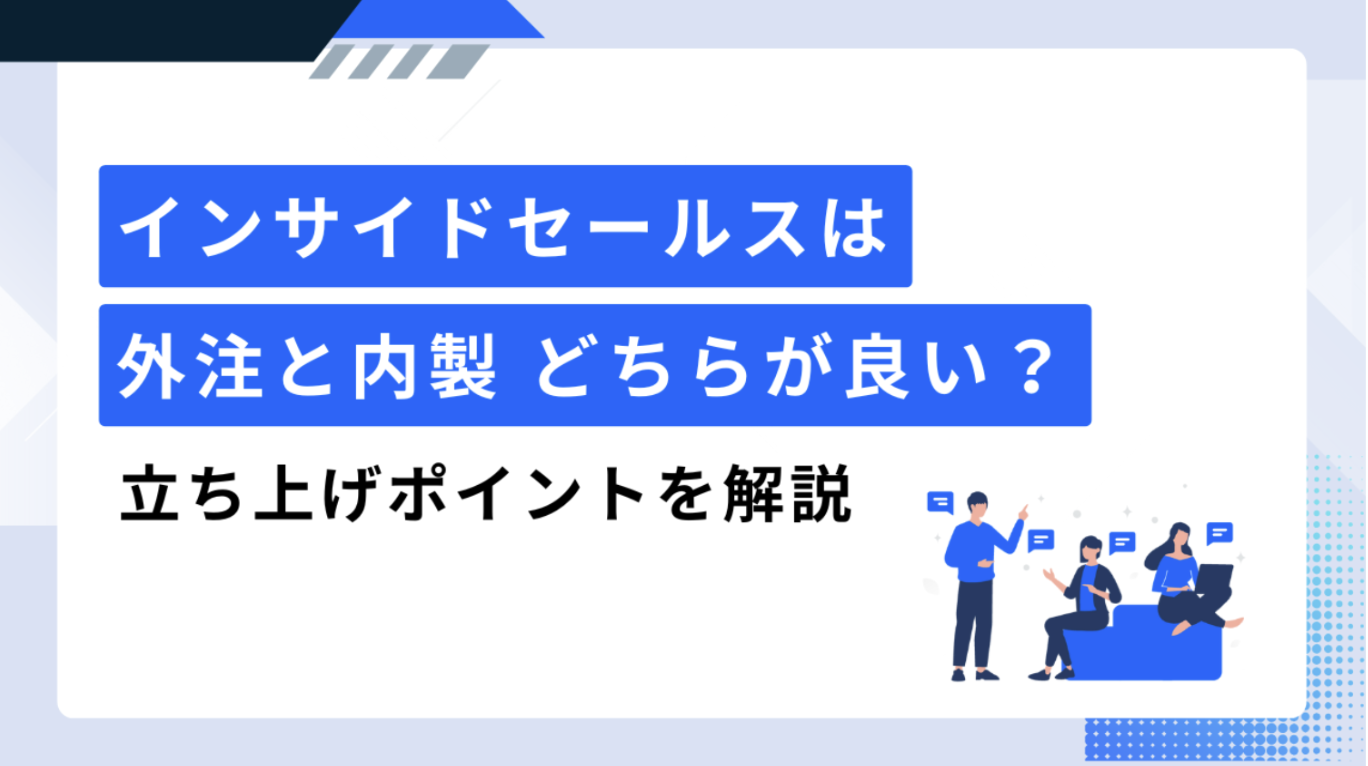
インサイドセールス(BDR/SDR)の外注・内製を徹底比較。立ち上げのコツを解説
「THE MODEL」というワードを聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?
多くの企業が効率的な営業活動を求め、インサイドセールスの導入を検討しています。その運用体制を外注するべきか、内製化するべきかで悩んでいるという声も増えています。本記事では、インサイドセールスの基本から、外注・内製・ハイブリッド型の各運用体制のメリット・デメリット、そして立ち上げのポイントについて詳しく解説します。
▶︎ROAS200%、月間アポ数8倍の実績あり|インサイドセールス代行事例集はこちら
1. インサイドセールスとは
インサイドセールスとは、電話やメール、オンライン会議などの非対面手段を活用して行う営業手法の1つです。従来の訪問型営業(フィールドセールス)とは異なり、電話やメールで顧客とコミュニケーションを図ることで、効率的な営業活動を行います。
セールスは「足で稼ぐ」ものと言われた時代もありましたが、この手法は、コスト削減や営業範囲の拡大、迅速な対応が求められる現代のビジネス環境において重要であると言えます。
2. インサイドセールスの運用体制の種類
インサイドセールスの運用体制には、大きく分けて「内製」「外注」「ハイブリッド型」の3つの種類があります。自社でチームを立ち上げて運用する内製型、専門の代行会社に業務を委託する外注型、それぞれの強みを活かすハイブリッド型など、企業の目的やリソースに応じた選択が必要です。
ここでは、それぞれの運用体制の特徴について詳しく解説します。
| 体制 | 内製 | 外注 | ハイブリッド型 |
|---|---|---|---|
| 概要 | インサイドセールスの業務を自社内で完結させる運用体制のこと | インサイドセールスの業務を専門の代行会社に委託する運用体制のこと | 内製化と外注の双方を組み合わせた運用体制のこと |
| 特徴 | ・PDCAサイクルを迅速に回せる・社内にノウハウが蓄積される・商材知識を活かした提案が可能・部門間の連携が取りやすい | ・即戦力の人材を確保できる・採用・育成コストを削減できる・柔軟な運用が可能・早期に成果を出しやすい | ・リソース不足を外部で補完できる・専門的なノウハウを取り入れやすい・段階的な内製化が可能・業務の優先度に応じた配分が可能 |
2.1 インサイドセールスの内製
内製とは、インサイドセールスの業務を自社内で完結させる運用体制を指します。自社の社員が直接、見込み顧客へのアプローチやフォローアップを行い、商談の創出や契約締結をします。
内製に向いている企業
- 立ち上げ経験者や社内に豊富なノウハウを持つ人材が社内にいる
- インサイドセールスチームに配置できる十分な人的リソースがある
- 立ち上げ時のデータ整備に必要なツール導入などに割ける予算がある
2.2 インサイドセールスの外注
外注とは、インサイドセールスの業務を専門の代行会社に委託する運用体制を指します。代行会社が見込み顧客へのアプローチやフォローアップを行い、商談の創出をサポートします。
外注に向いている企業
・フィールドセールスの経験はあっても、社内にインサイドセールスの経験者がいない
・人員を確保できない
・短期間で成果を出したい
2.3 外注と内製のハイブリッド型
ハイブリッド型とは、内製化と外注の双方を組み合わせた運用体制を指します。例えば、初期段階では外注を活用し、ノウハウを蓄積しながら徐々に内製化を進める、または特定の業務のみを外注し、その他の業務は内製化するなどの方法があります。柔軟性を持ちながらも質を維持するために効果的です。
ハイブリッドに向いている企業
・予算に制約はあるが、質を維持したい
・自社のリソースは重要顧客の対応に充てたい
・新規事業の立ち上げで迅速に結果を出す必要がある内製に向いている企業
・立ち上げ経験者や社内に豊富なノウハウを持つ人材が社内にいる
▶︎ROAS200%、月間アポ数8倍の実績あり|インサイドセールス代行事例集はこちら
3. インサイドセールス運用体制別のメリット・デメリット
インサイドセールスの運用体制は、内製・外注・ハイブリッドの3つに分かれ、それぞれにメリットとデメリットがあります。人材採用や育成、予算、立ち上げまでの期間など、自社の条件に合った運用方法を選択しましょう。
3.1 インサイドセールス内製のメリット・デメリット
内製のメリット
- 自社にノウハウが蓄積される
自社の社員が業務を行うことで、インサイドセールスに関する知識が社内に蓄積され、今後の別の事業部でのインサイドセールス発足時や、その他の戦略立案や業務改善に活かすことができます。
- 自社の事業、商材理解がある担当者がセールスできる
自社の社員であれば、自社のサービスや製品に対する深い理解があるため、顧客への的確な提案や対応が可能です。
- フィールドセールスとの連携が取りやすい
社内の営業チームと密に連携できるため、インサイドセールスで得た情報をスムーズにフィールドセールスへ引き継ぐことができます。
- セキュリティが安心
顧客データや営業情報を外部に出さないため、情報漏えいのリスクが低くなります。特に個人情報や機密情報を扱う企業にとっては、セキュリティの観点から内製化のメリットは大きいです。
内製のデメリット
- 立ち上げにはノウハウが必要
インサイドセールスの成功には、営業戦略や業務フローの設計、適切なKPIの設定などのノウハウが不可欠です。フィールドセールスの経験を持っていても、インサイドセールスの経験がない場合、運用が難しくなることがあります。
- 成果が出るまでに時間がかかる
内製化はゼロからチームを構築するため、採用や教育、業務フローの整備などに時間を要します。短期間での成果を求める場合には内製化には向いていません。
- 設備やツールのコストがかかる
インサイドセールスの運用には、CRMやSFA(営業支援ツール)などのシステム導入が必要です。これらのツールの導入・運用コストがかかるため、初期投資が大きくなる可能性があります。
- 採用、育成コストがかかる
インサイドセールスに適した人材を採用し、戦力化するには時間とコストがかかります。特に、インサイドセールスは営業スキルだけではなく、マーケティング知識も持っている必要があるため、採用は容易ではなく、教育にも時間がかかります。
商談数にコミットするインサイドセールス代行支援サービスを見る
3.2 インサイドセールス外注のメリット・デメリット
外注のメリット
- 設備や人材コストなどの固定費を削減できる
外注を利用することで、インサイドセールスに必要な設備や人材を社内で整備する必要がなく、固定費を大幅に削減できます。例えば、アプローチリストのためのリスト作成ツールや、アプローチ管理をするためのSFAやMAツールなどの費用がそれにあたります。
- 立ち上げがスムーズ
外注先には専門的な知識と経験があるため、インサイドセールスの立ち上げがスムーズに進みます。短期間で業務を開始できるため、急ぎでリード獲得や育成をしたい企業にとっては大きなメリットです。
- プロによる早期の成果創出が可能
外注先には多くのクライアントでの実績があるため、その経験を活かして即戦力としてリード獲得やアポ獲得が期待できます。
- 自社に新たなノウハウがたまる
外注先からフィードバックを受けることで、ノウハウが社内に溜まっていきます。外部の視点や知見を取り入れることで、自社の営業手法の改善点や新たな戦略を見つけることができます。
- 必要な時だけ依頼ができる
売上計画や、手元のアプローチリストの数に応じて柔軟に依頼ができ、支援会社によってはスポットでの契約が可能です。万が一、自社内の営業組織としてインサイドセールスが合わなかった場合も活動を止めることができます。
外注のデメリット
- 代行会社との連携やコミュニケーションが必要
円滑な営業活動のために、外注先の企業とのコミュニケーションが必要です。窓口として対応する人を一人用意しなければならず、効果検証のスピードも内製している場合と比較すると落ちてしまいます。
- 委託先によっては自社にノウハウがたまらない
委託先の企業にもよりますが、業務を外部に依頼する以上、社内に知見が溜まりづらくなります。特に、お客様の反応などの定性情報は定量情報に比べると共有が難しく、社内に知見が蓄積されにくいでしょう。将来的に内製化を目指す場合、ノウハウをどうやって移管するかが課題になる可能性が高いです。
▶︎ROAS200%、月間アポ数8倍の実績あり|インサイドセールス代行事例集はこちら
3.3 インサイドセールス ハイブリッド型のメリット・デメリット
ハイブリット型のメリット
- 内製化までのスピードが早い
外部の知見を活用しながら、インサイドセールスの運用が軌道に乗ったタイミングで内製化を進めることで、効果を出しつつ最短で自社での運用を軌道に乗せることができます。
- 自社に知見がたまる
外部パートナーと協力しながら業務を進めるため、完全外注に比べるとノウハウの蓄積がしやすく、将来的に完全内製化する際の準備が整いやすくなります。
- 採用コストが不要
新たにインサイドセールスの担当者を採用する手間やコストを削減でき、自社に適切なインサイドセールス人員を、外部で揃えることができます。
- 外注と比べてセキュリティのリスクが低い
業務の一部を社内で管理するため、外部への情報漏洩リスクを抑えることができます。
ハイブリット型のデメリット
- 人材育成のコストがかかる
ハイブリッド型では、内製化を進めるために社内のメンバーの育成が必要となり、教育コストが発生します。
- コストが高騰する可能性
外注費用と内製のためのリソース確保を並行して行うため、運用コストがかさみます。3つの運用体制の中で最もコストがかかる可能性が高いです。
- 外注先との連携や調整が必要
内製と外注を組み合わせるため、情報共有や業務の進捗管理が複雑になり、スムーズな連携が求められます。どこまで自社で対応をし、どこから外注企業にお願いをするのかなど、フローを含めて事前に決めておくことが必要です。
4.【体制別】インサイドセールスの立ち上げポイント
インサイドセールスの運用体制をどのように構築するかは、その後の事業成長に大きく影響します。ここでは、内製化、外注、ハイブリッド型のそれぞれにおける立ち上げポイントについて詳しく解説します。
4.1 インサイドセールス内製の流れ
①社内体制の確立
まず営業部門やマーケティング部門との連携体制を構築し、インサイドセールス専任のチームを編成します。これにより、部署間の連携がスムーズになり、業務の範囲や責任分担が明確になります。また、インサイドセールスと営業部門、インサイドセールスとマーケティング部門とのKPIや言葉の定義のすり合わせもこのタイミングで行うと良いでしょう。
②人材の採用、異動
インサイドセールスに必要なスキルや知識を持つ人材を採用、または既存の社員を異動させます。特に、顧客対応に強い営業スキルを持つ人材や、データ分析に精通した人材、マーケティングの考え方を理解している人材を選ぶことがポイントです。必ずしも、フィールドセールスで売上をハイ達成している人がインサイドセールスに向いているわけではありませんので、注意しましょう。
③人材の教育
採用した人材には、営業スキルや顧客対応の教育を行います。特にインサイドセールスは電話やメールでのアプローチが多いため、提供するサービスの基礎知識を身につけ、ケーススタディを通じて細かなサービスの使用を理解したりと、インプットが重要になります。
電話ロープレなどのトレーニングも効果的です。
④システムやツールの導入
必要に応じてCRMシステムやSFA(営業支援)ツール、MA(マーケティングオートメーション)ツールを導入すると良いでしょう。これにより、営業活動をデータに基づいて管理し、チーム全体での情報共有が容易になり、業務の効率化を図ることができます。
商談数にコミットするインサイドセールス代行支援サービスを見る
4.2 インサイドセールス外注の流れ
①外注する業務範囲の決定
まずは、インサイドセールス業務の外注範囲を明確に決めます。リード獲得やアポイント獲得、商談設定など、具体的な業務内容を洗い出し、どこまでを外注で対応するかを決めることが重要です。また、電話のヒアリング項目は何か?得た情報はどのツールに残すのか、どの形式で報告してもらうのか、といった業務内容を明確にすることで、効率的かつ適切な外注先を選定できます。
②代行会社の選定、比較
次に、外注先となる代行会社を選定し、複数の候補を比較します。各社の実績や得意分野をチェックし、自社のニーズに最適な会社を見つけることが重要です。また、価格やサポート体制、対応スピード、使用できるツールの種類、普段のやりとり(メールやチャットツールは使えるか)も比較ポイントとなります。
③代行会社との打ち合わせ(支援内容や契約条件、見積もりのすり合わせ)
選定した代行会社と打ち合わせを行い、支援内容や契約条件を明確にすり合わせます。具体的な業務フローや納期、報酬体系を合意し、見積もりを基に契約を締結します。この段階で、双方の期待値を調整し、円滑な業務進行を確認することが重要です。
4.3 インサイドセールス ハイブリッド型の流れ
①外部の支援により段階的に体制を構築
外注の流れ同様、依頼する業者を選定し、まず代行会社の支援を受けながら運用の立ち上げを迅速に行います。外部のノウハウを活用することで短期間での立ち上げが可能になります。ですが、自社サービスをよく把握しているのは自社の社員であるため、代行会社への事前のサービス概要や料金体系などのインプットはしっかり行いましょう。
最初は外部の力を借りながら、段階的に自社内の体制を整えていきます。
②自社チームの育成
立ち上げ後は、自社のインサイドセールスチームの育成に力を入れ、営業スキルや商材理解を深めるトレーニングを行います。また、業務フローの整備やSFA・MA・CRMなどのシステムの導入を進め、自社のノウハウを蓄積していきます。外部支援を受けながらも、次第に自社での運用が中心となるよう体制を強化します。
③内製化へと移行
最終的には、外部の支援を段階的に減らしながら、徐々にインサイドセールスを内製化していきます。自社内での知識やノウハウが蓄積されてくれば外注への依頼範囲を狭めていきましょう。外注から完全に内製化するまでの期間は、企業の規模や体制によって異なりますが、引き継ぎがあるため、6ヶ月〜1年を目安とされています。
商談数にコミットするインサイドセールス代行支援サービスを見る
▶︎ROAS200%、月間アポ数8倍の実績あり|インサイドセールス代行事例集はこちら
まとめ 自社にあった適切な方法でインサイドセールスの体制構築をしよう
インサイドセールスを成功させるためには、自社のサービス内容や営業戦略、かけられるリソースに応じた運用体制を選択することが重要です。内製、外注、ハイブリッド型のそれぞれの特徴を理解し、最適な方法でインサイドセールスを立ち上げ、運用していきましょう。
マーケティングコミットでは、インサイドセールス(BDR/SDR)の支援を行っています。ご興味をお持ちの方はぜひ以下の資料をダウンロードして見てください。
【マーケティングコミットのインサイドセールス代行サービス】
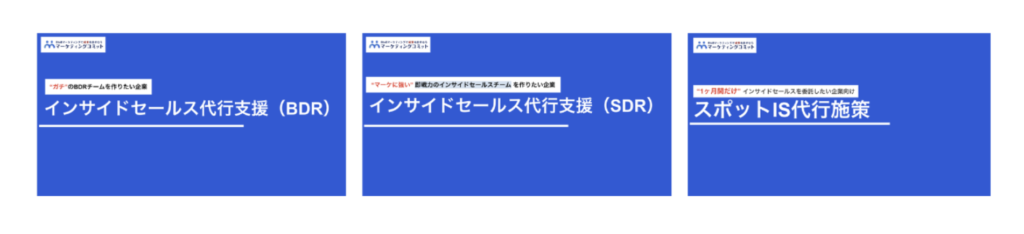
マーケティングコミットでは、SDR(Sales Development Representative)によるリード育成から、BDR(Business Development Representative)を活用した新規開拓まで、一気通貫で貴社の営業成長を支援します。インサイドセールスの強化を検討している方は、ぜひ詳細をご覧ください。
BDR(アウトバウンド)代行支援サービス資料をダウンロードする
SDR(インバウンド)代行支援サービス資料をダウンロードする
【ISリソース不足を解決】スポットIS代行サービス資料をダウンロードする
関連記事:
インサイドセールスの外注でROAS200%超え。アウトバウンド代行の裏側【事例|sincereed株式会社様】
インサイドセールスは外注、内製どちらが良い?立ち上げポイントを解説
営業フリーランス・業務委託の活用法|採用難でも即戦力を確保する方法
インサイドセールス「外注」「内製」を徹底比較。立ち上げのコツを解説
「月間0アポ→20件へ」インサイドセールス(SDR)の仕組み化と休眠リードの商談創出の裏側 〜成功の鍵は徹底した“伴走支援”〜【CATS株式会社様/導入事例】
関連資料:
ROAS200%、月間アポ数8倍の実績あり|インサイドセールス代行事例集はこちら
▼【BtoBマーケ/セールス特化】即戦力BtoBマーケ・セールス業務委託人材一覧はこちら|株式会社マーケティングコミット▼